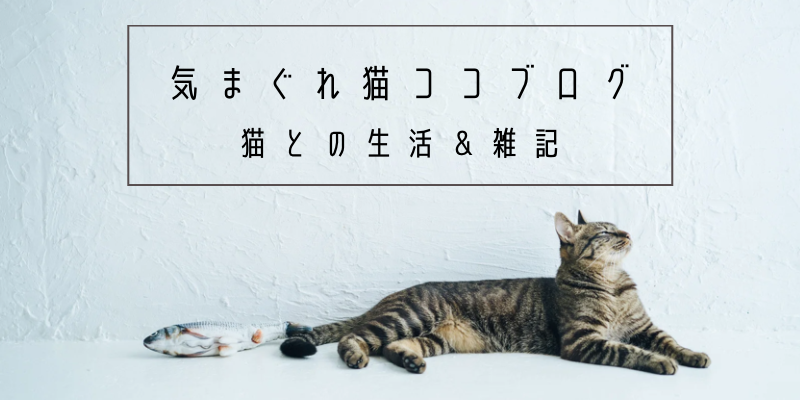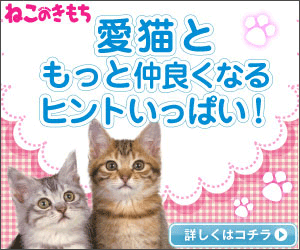猫を飼うなら、保護猫を迎え入れよう!
みなさんは、保護猫をご存じでしょうか?
保護猫とは、文字通り何らかの理由で保護されている猫のことです。
これらの猫は、虐待やネグレクトなどで傷ついた猫、多頭飼育崩壊、迷い猫、捨て猫などの様々な理由で保護されています。辛い思いをしている猫達が多く、飼い主が見つからなければ殺処分される運命にある猫も多いのです。
また、誰かに保護されることなく、外で暮らしている猫もいます。気ままな生活をしているかと思いきや、そうした猫たちは、虐待にあったり、交通事故にあったりと過酷な生活をおくっています。
自分にも何かできることはないかと思っていましたが、こうした不幸な猫たちを助ける活動をしている方々がいますので、僅かですが寄付をすることで応援したいと思います。
殺処分にされる猫の数
2019年4月1日~2020年3月31日に保健所に持ち込まれた猫は53,342匹です。2割が飼い主からで、残りの8割は所有者が不明です。
このうち返還数は305匹、譲渡数が25,636匹。
殺処分された猫は27,108匹です(犬・猫の引取り及び処分の状況 環境省_統計資料より)。
1年間にこんなに多くの猫が殺処分されているのです。
この現状を変えるためにも、猫が好きで猫を飼いたいとお考えの方は、ぜひ保護猫を迎え入れることも考えてほしいと思います。
保護猫を飼うことで殺処分される猫を減らし、命を助けることができます。
保護猫のトリセツ本のご紹介
保護猫を飼う方法や保護猫のリアルについて、書かれた本をご紹介します。
「ねこ活はじめました かわいい!愛しい!だから知っておきたい保護猫のトリセツ」
この本では、猫を飼おうとペットショップめぐりをしていたご家族が保護猫のことを知って現状を憂い迎え入れるまでの様子が書かれています。
このご家族は始めは子猫を飼う予定でしたが、飼い主にネグレクトを受けていた4歳の三毛猫しらすちゃんと運命の出会いを果たし飼うことを決めます。
この本を読んで、保護猫の悲しみや子猫にこだわらず成猫を迎え入れることの良さも感じられました。保護猫を飼いたいと思っている方は、参考になりますのでぜひとも読んでみてください。
保護猫を迎え入れる方法
保護猫を迎え入れるには
- 保健所や動物愛護センターなどの公的機関
- 動物保護団体や猫カフェなどの民間団体
- 捨て猫を保護する
- 里親募集サイト
- SNS掲示板
などいろいろな方法があります。
この中で私がお勧めするのは、保健所や動物愛護センターなどの公的機関や動物保護団体や猫カフェなどの民間団体です。
これらの団体は譲渡条件は厳しいですが、事前講習や飼育の相談、トライアル飼育を受け付けている場合がありますので、保護猫を迎え入れるのに慣れていない人にとっては安心して申し込みができます。
里親募集サイトやSNS掲示板などでは、基本的に個人間のやり取りになりますので、トラブルに巻き込まれる危険性があります。
ボランティア団体が募集している場合もありますが、中には偽ボランティアが潜んでいることがあります。
野犬ビジネスという言葉を聞いたことがあるでしょうか?
これは、野良犬に餌付けをして繁殖をさせ、母犬から子犬を奪い里親募集サイトなどで寄付金と称して金銭を得るという闇のビジネスです。こうした詐欺にあわない為にも自分の目でしっかりと団体を見極めてから里親に応募することをお勧めします。
迎え入れる条件や手続き方法は各団体によって違いますので、ホームページで確認してください。下記にURLを貼っておきますのでそちらをご覧になってください。
環境省 収容動物検索情報サイト
保護活動団体の一覧(都道府県)
動物愛護センターで里親になる場合
各都道府県の動物愛護センターによって対応は違いますが、今回は「秋田県動物愛護センターワンニャンピアあきた」での譲渡手続きや譲渡条件をご紹介します。
犬猫の譲渡について
| 実施期間 | 年度中随時実施 |
|---|---|
| 実施場所 | 秋田県動物愛護センター(秋田市雄和椿川字奥椿岱1) |
| 受付方法 | 動物愛護センターにて受付しております。 ※予約による受付は行っておりません。センターで実際に譲渡動物を見ていただきお申し込みください。 |
| 譲渡動物 | 子犬、成犬、子猫、成猫 ※病気や行動等について審査し、センターが譲渡適正があると判断した犬猫 |
| 譲渡方法 | 譲渡動物は動物愛護センターや合同譲渡会で展示するほか、動物愛護センターホームページ等に掲載されます。センターに来所していただき受付にて面接等を行いながら譲渡への手続きを進めてまいります。 申込内容を確認させていただきますので、必ずしもご希望に添えない場合があります。 |
| 譲渡条件 |
|
| 譲渡者へのお願い | 譲渡前に、飼い方等の講習を1時間程度受けていただきます。 譲渡の際には、他人に迷惑をかけないよう終生責任を持って飼っていただく旨の誓約書を提出していただきます。 |
(ワンニャンピアあきたホームページより引用 https://wannyapia.akita.jp/)
受付方法
動物愛護センターにて随時受付をしております。
※予約による受付は行っておりません。センターで実際に保護猫を見ていただいてからお申し込みください。
譲渡の流れ
保護猫には、動物愛護センターや合同譲渡会に行けば出逢えます。動物愛護センターのホームページにも掲載されておりますので、事前にそちらを確認されると良いでしょう。
譲渡の手続きは、センターにお越しいただき受付にて、面接を行いながら進めていきます。
申込内容を確認させていただいてからの決定になりますので、ご希望に添えない場合があります。

譲渡条件
- 原則として秋田県民であること。
- 動物の種類、年齢などに合わせて、適正に飼養管理をすること。希望される方の動物飼養状況なども加味されます。
- 関係法令を必ず守り、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること。
- 譲渡後に不妊・去勢手術を実施すること。
- 飼養について家族全員の同意が得られていること。
特に高齢者家族の場合は、親族などによる継続飼養の支援が担保されていること。 - その他センターが求める誓約事項を必ず守ること。
※譲渡前に、飼い方などの講習を1時間程度受けていただきます。
譲渡の際には、他人に迷惑をかけないように動物がその命を終えるまで適切に飼っていただく旨の誓約書を提出していただきます。
動物保護団体で里親になる場合
動物保護団体、猫カフェなどの民間団体はたくさんあって、各団体によって譲渡手続きや譲渡条件は違います。
ここでは、一般的な保護猫団体での里親への譲渡条件や手続き方法についてご紹介します。

里親への譲渡条件
- ペット可の住居に居住していること
- 終生において完全室内飼育をすること
- 終生愛情と責任を持って飼育をすること(絶対に捨てないこと)
- 伴侶動物としてのみ飼育をすること(再譲渡、販売、貸出、展示、動物実験などに利用しないこと)
- 譲渡後に不妊・去勢手術を実施すること
- 未成年者、定職についていない方には譲渡不可
- 単身世帯や60歳以上の家族のみ方への譲渡は原則として不可(万が一の時に引き継いで終生飼養の責任を負っていただける後見人がいる場合は、認めている団体もある)
- 上記の条件を満たしている場合でも、団体が譲渡不適格と判断した場合は、お断りする場合がある
※譲渡時に寄付金や負担金(ワクチン接種費用、ウイルス検査費用、避妊去勢手術費など)を求められる場合があります。各団体のホームページよりご確認ください。
譲渡手続き
譲渡手続きの流れをご紹介します。
- ウェブサイトで保護猫の確認をし、面会の申し込みをする(電話受付をやっている団体もあります)
- 面会
- トライアル飼育
- 引き取り決定
- 飼育開始
※各団体では譲渡会を行っている場合がありますので、そちらに参加してみるのもお勧めです。
最後に
今回は、保護猫を迎え入れることについてご紹介してきました。
私が猫を迎え入れたのはペットショップからで、猫を飼うまでは保護猫のことはよく知らず関心もありませんでした。
猫を飼い始めて、ペットショップの動物達への扱いや売れ残りの問題を知り愕然としました。人間によって、動物達がこんなに酷い目にあっているのかと悲しくなりました。
ペットショップの問題については、以前書いたブログをお読みください。

このブログを通じて、少しでも猫が置かれている現状を知っていただいて、殺処分される猫が減ることを望みます。
動物を飼ったら、動物が命を終えるまで愛情を持って飼い続けてください。
もし飼えなくなっても、簡単に捨てたりしないで里親を探してください。
里親が見つけられなかったとしても、費用を負担すれば預かってくれる動物保護団体もあります(悪徳な団体もありますので、自分の目でしっかりと見極めることが必要)。
不幸な動物たちを減らす為には、飼う側のモラルが重要です。
可愛いからと安易に飼わずにしっかりと責任のある対応をしてください。
それができないのなら、動物を飼わないでください。